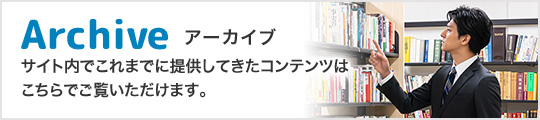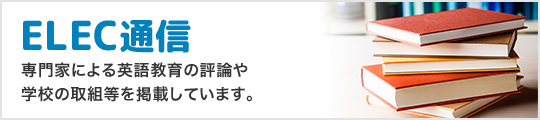やさしく読める英語ニュース
中学校の英語教科書で使われている語彙で読めるように編集しています。
それ以外の単語や固有名詞などは「キーワード」欄で説明してあります。
英語ニュースの本文・音声は、授業でご自由にお使いください。
制作協⼒ : 株式会社ジャパンタイムズ ⾳声収録 : ELEC録⾳スタジオ
What's new最新のご案内
一覧を見る- 2024/04/22NEW 「やさしく読める英語ニュース0422」記事を更新しました。
- 2024/04/02 「文部科学省後援 2023年度ELEC春期英語教育研修会/小学校英語教育workshop」閉会
- 2023/12/15 年末年始休業のお知らせ

Information教材や指導案を探す
授業づくりにお使いいただける教材や、
指導案をご案内しています。
全国の教育委員会の実践報告などへのリンクも
網羅しています。
-
- ”理系こそ英語!”
- 理系学生から英語が苦手、英語ができない、という声が多くあります。 なぜ理系は英語が苦手なのでしょうか。 そして、そこに何らかの解決方法はあるのでしょうか。 長年にわたり大学で実践・研究をされている「理系のための英語教育」について、 東京理科大学教授 片山七三雄 先生が「ELEC通信」に寄稿してくださいました。 是非お読みください。 理系のための英語教育‥考
-
- パンデミック
- 中国武漢から始まったCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の流行が日本にも押し寄せています。 私は医学の門外漢ですのでこの病気自体について詳しく述べることは差し控えたいと思いますが、ここでは一般的に「パンデミック」と呼ばれる状態について考察してみようと思います。 1) パンデミック(pandemic)とは、ある感染症が国中あるいは世界中で流行することを言います。 WHO (World Health Organization)(世界保健機関)では新型コロナウイルスの感染は現状ではパンデミックに当たらないが、ウイルスの感染拡大の封じ込めに全力を尽くすべきだと強調しています(2020年2月25日現在)。一方、アメリカの米国立アレルギー・感染症研究所所長は、「我々は明らかにパンデミックが起きる瀬戸際にいる」との認識を示しました。つまり 2) 渡航により感染例に遭遇する中国以外の諸国の対処能力に左右される局面にあるとし、ヒトからヒトへの感染が連鎖し始めている状態となっていると言っています。現在の日本や韓国のように感染源が特定できなくなっている事例が増えているのを見るとパンデミックが生まれつつあると指摘し、このような国が多数になると後の祭りとしています。 一般的にインフルエンザは、抗原が特異的に抗体を認識し結合するため新たに派生的な型(亜型)が出現して大流行をすることがあります。 3) もともとトリに存在していたこれらの亜型が何らかの理由によりヒトからヒトへの感染性を獲得すると、ヒトはそれに対する免疫を持っていないため世界的な大流行を起こすことになります。これがパンデミックです。 これまでにも数十年に一度、このようなパンデミックが起こっています。古いところでは1918年に起きたスペイン風邪、1957年のアジアインフルエンザ、そして1968年には香港インフルエンザが起こりました。記憶に新しいところでは、2003年のSARSコロナウイルス、2015年のMERSコロナウイルスがあります。 スペイン風邪は、第一次世界大戦中の1918年に北米、ヨーロッパではじまりましたが、第一波では致死性はあまり高くなかったとされています。いったんは収まりましたが、同年晩秋にフランス、米国で再び流行が起こり、今度は10倍の致死率となりました。特に若年層に死者が多く、死者の99%が65歳以下であったとされています。1919年初頭には第三波が起こりました。こうして一年の間に3度の大流行があったのです。 スペイン風邪は出血を伴う一次性のウイルス性肺炎を起し、短期間に重症化して死に至ったようです。もちろん当時は病を特定することすら難しかったので、最初は黒死病の再来とか脳脊髄膜炎などと疑われました。有効なワクチンや抗生物質などもなく、感染を予防するために採られた方法は、患者の隔離、接触者の行動制限、消毒、個人的に衛生に気をつけるなどといった初歩的な方法のみでした。のちに集会の禁止や学校の閉鎖が行われ伝播速度を遅くすることはできましたが、患者数を減らすことはできませんでした。この間、世界的な患者数はWHO調べで世界人口の25-30%におよび、死亡者数は4000万人に上りました。日本でも2300万人が罹患し38万人が死亡したとされています。 インフルエンザウイルスが初めて分離されたのは1933年のことでした。 1957年にはアジアインフルエンザが流行しましたが、このころにはインフルエンザに対するワクチンが開発され、細菌性の肺炎を治療する抗生物質も開発済みでした。2月に中国のある地域で発生したこのインフルエンザは3月には中国中、4月後半には香港に達し、5月には日本とシンガポールでウイルスが発見されるなど素早い速度で広がりました。一方、欧米では感染拡大に2、3か月かかるなど国によって伝播速度が異なりました。ウイルスが国に入っていても感染拡大のタイミングは国によって異なったということですが、その理由ははっきりとわかっていません。 4) いったん流行が始まるとスペイン風邪の時と同様に爆発的な感染拡大が見られましたが、致死率はスペイン風邪よりかなり低く、患者は学齢期児童に集中していました。死亡者は高齢者と乳幼児に限定されていました。第二波では、高齢者に感染が拡大し、より高い致死率となりました。世界中で200万人の超過死亡者数が報告されています。 しかし最初の流行から一週間以内にWHOではウイルスを分離分析し、ウイルスサンプルが世界中のワクチン製造者に配布されました。8月には米国で、10月には英国で、そして日本では11月にワクチンが使用可能となりましたが、まだまだ数は充分でなく、集会の禁止と学校閉鎖のみが感染拡大を止める唯一の方法だったようです。 1968年の香港インフルエンザはアジアインフルエンザよりさらに軽度で、爆発的なアウトブレイクもなく、香港インフルエンザに起因する死亡者数は前年度の季節性インフルエンザより少なかったとさえ言われています。前のパンデミックでの免疫を持っていた人たちの間でそれが防御的に働いたようです。 季節性インフルエンザではこれまでの経験からワクチンが用意され、その供給が需要を上回るため大流行が起こることはありませんが、新型インフルエンザのパンデミックの場合は発生からワクチン製造までに6か月かかり、需要拡大期に供給することができません。また患者数が一気に増え、おまけに医療関係者も罹患するため医療機関の許容量を超えてしまい、医療システムが破綻することになります。また 5) パンデミックインフルエンザでは流行の規模が膨大であり、学校の閉鎖や集会の禁止も長期化するため経済活動も影響を受け、企業の存続や世界経済への深刻な影響も懸念されます。 新型インフルエンザの流行の際にどのような症状が現れるか、感染がどのような展開を見せ、どのような集団で重症化するかなどについての予測は非常に難しいのですが、パンデミックが起こった際にその疾病の特徴と流行の様相を素早くとらえ、患者からの臨床情報を調査、分析し、それらを共有して、それに合わせて迅速な治療や対策をとることが必要だとされています。 今まさに日本でのコロナウイルス対策は上記の局面を迎えているように思います。早くウイルスの実相を解明し、それに対する処方を確立し、それをできる限り早く供給していくことが必要です。学校閉鎖や集会禁止といった行動規制のみでなく、医学的な対応も同時に進めて、このウイルスによる被害を最小限にとどめたいものです。 参照:感染症・予防接種ナビ及び国立感染症研究所の記述を参考にいたしました。 下線部を英語に訳してみましょう 1) パンデミック(pandemic)とは、ある感染症が国中あるいは世界中で流行することを言います。 2) 渡航により感染例に遭遇する中国以外の諸国の対処能力に左右される局面にある。 3) もともとトリに存在していたこれらの亜型が何らかの理由によりヒトからヒトへの感染性を獲得すると、ヒトはそれに対する免疫を持っていないため世界的な大流行を起こすことになります。 4) いったん流行が始まるとスペイン風邪の時と同様に爆発的な感染拡大が見られましたが致死率はスペイン風邪よりかなり低く、患者は学齢期児童に集中していました。 5) パンデミックインフルエンザでは流行の規模が膨大であり、学校の閉鎖や集会の禁止も長期化するため経済活動も影響を受け、企業の存続や世界経済への深刻な影響も懸念されます。 英訳例 1) Pandemic refers to the spread of an infectious disease across a country or around the world. 2) The situation is dependent on the coping ability of countries other than China that encounter cases of infection through travel. 3) If these subtypes, which originally existed in birds, become able to infect and be transmitted by humans for any reason, humans, who never had immunity to it, will cause a worldwide pandemic. 4) Once the epidemic started, an explosive expansion of the infection was seen just with the Spanish flu. However, the mortality rate was much lower than that of the Spanish flu, and the patients concentrated in school age children. 5) When there is a pandemic, the infection scale is enormous. School closures and bans on meetings are prolonged, so economic activity is affected and there is a fear for the survival of companies and as well as concerns about the pandemic’s serious impact on the global economy. なお、今回を持ちまして「高校生のための理系英語」の連載は終了させていただくこととなりました。対象の分野は多岐にわたりましたが、理系のトピックの時事的考察とその英語表現ということに専心いたしました。皆さんの理系英語の習得に少しでもお役にたてていれば幸いです。長い間ご愛読いただきましたことに心より御礼申し上げます。
-
- 竜巻
- 今年の日本列島は異常な気象による災害が多発しています。台風による被害も例年以上に大きく酷くなっています。これらは地球全体の温暖化の影響とも言われていますが、原因はそれだけとは限定できません。1) およそ気象現象には様々な要因が複合的に絡まり合って想定以上の被害をもたらすことが多いのです。 2) 備えあれば憂いなしといいますが、気象現象に対して十分に備えられれば被害は少なくて済みますが、往々にして準備した規模より大きかったり、準備できないほど突然起こったりして人々を災害に巻き込んでしまいます。3) 突然起こって予期できない現象のひとつに竜巻があります。「オズの魔法使い」でも竜巻によって飛ばされたところからお話が始まるように昔からアメリカのカンザスなど中南部の内陸では竜巻がよくおこります。北極海からの寒気とカリブ海からの暖気がぶつかることで大気が不安定になって年間1000個ぐらい起こるのですが、近年では日本でも内陸のみならず海沿いの県でもよくおこっているようです。山沿いでは下降気流のため比較的発生しにくいようです。 1961年~2015年 竜巻発生分布図(全国) 出典:気象庁ホームページ 今回は竜巻について学んでみましょう。 竜巻は一言でいえば「激しい空気の渦巻で、大きな積乱雲の底から漏斗状に雲が垂れ下がり、陸上では巻き上がる砂塵、海上では水柱を伴う」ものですが、雷を起すことで知られる積乱雲が発達した結果起こります。地上で何らかの原因で突風が回るように吹くことがあります。その時 4) 前線や低気圧、台風などのために空気が暖められると上昇気流と言って周りの空気を吸い上げるようにして渦巻きを上方へ引っ張ります。気圧の差が大きいとそれがどんどん細くなって、その分スピードが増して細くて強い気流になり、すごい勢いの上昇気流が起こります。それが竜巻です。なお、積乱雲由来でそこから垂れ下がった漏斗状の雲が地面に達したもののみを竜巻というと気象庁は定義づけています。竜巻が起こり始めるとまずゴミや軽いものが吹き上げられます。運動会でプログラムやお弁当の包み紙が飛び散ったと思うや否やそれが急に強くなり、ゴーッと音がして机やテントなども飛ばされてしまう情景をTVなどで見たことがあるでしょう。ひどい時には車や家が壊されることもあるほどの破壊力です。その時には当事者は分かりませんが、離れて見ていると地面から上空に達する漏斗状の雲が見えるはずです。 建物の窓からも風は侵入してきますからできるだけ窓の無い部屋や頑丈な机の下にもぐり頭を保護します。外の様子が気になりますが窓から外を見ていると吹き込んできた風で窓ガラスが割れ怪我をすることがありますのでカーテンを引くなどして注意しましょう。屋外で竜巻に出会ったら、できるだけ頑丈な建物に潜り込むかその陰に隠れます。付近にそういった建物がない場合は側溝や窪地に身を伏せます。 遠くでゴロゴロと音がしたり冷たい風が吹いたり黒い雲が見えたら積乱雲が近づいている証拠です。人によっては耳鳴りがしたりすることもあります。積乱雲が近づくと雷が起きたり、竜巻が起こったりしますのでその気配を感じたらすぐに行動を起して安全な場所に身を隠しましょう。 5) 一口に竜巻と言っても、上に吹き上げる竜巻や上から下へ吹き付けるダウンバースト、横へ転がっていくガストフロントなどの変形があります。ダウンバーストは積乱雲から気流が下降し地表にたたきつけられ水平に吹き出します。またガストフロントは重い冷気のかたまりが周りの温かい空気の外側へ流れ出すことです。下表で比較してみましょう。 気象庁HP 主な突風の種類より http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/tornado1-1.html 出典:気象庁ホームページ 日本では年間20-30個程度ですが9月10月に発生することが多いようです。これらはいずれも突発的に起こり予期することが難しいので気配を感じたらすぐに避難しましょう。 下線部を英語に訳してみましょう 1) およそ気象現象には様々な要因が複合的に絡まり合って想定以上の被害をもたらすことが多いのです。 2)備えあれば憂いなしといいますが、気象現象に対して十分に備えられれば被害は少なくて済みます。 3)突然起こって予期できない現象のひとつに竜巻があります。 4)前線や低気圧、台風などのために空気が暖められると上昇気流と言って周りの空気を吸い上げるようにして渦巻きを上方へ引っ張ります。 5)一口に竜巻と言っても、上に吹き上げる竜巻や上から下へ吹き付けるダウンバースト、横へ転がっていくガストフロントなどの変形があります。 英訳例 1) In general, various factors are intricately intertwined when meteorological phenomena cause more damage than expected. 2) There is a saying “No worries if prepared”, and damage can be mitigated if one is sufficiently prepared for meteorological phenomena. 3) One of the unexpected phenomena that occur suddenly is the tornado. 4) When air is warmed due to the front, low pressure, typhoon, etc., it is called ascending current, which draws up the surrounding air and pulls the spiral upward. 5) There are various deformations for the term “tornado”, such as tornado that blows up, downburst that blows from top to bottom, and gust front that rolls sideways.
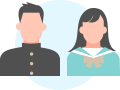
Column高校生のための理系英語
このコラムでは、
理系英語を題材として、
論理的な思考⼒・表現⼒を⾝につける
英⽂の読み⽅を紹介しています。

Event & Trainingイベント・研修情報
英語教育に関する、児童・⽣徒向けイベントや、
教員向けの研修会の情報などを掲載しています。
英語教育に関する、児童・⽣徒向けイベントや、
教員向けの研修会の情報などを掲載しています。
- 2024/04/26 『学校の未来図』~米田謙三先生に学ぶ、英語教師のための生成AI活用術~
- 2024/04/23 「英語っておもしろい!」生徒の探究心が高まる 教科横断型授業の実施ノウハウ
- 2024/04/23 【シリーズ「生成AI実践ガイド」入門編】教材の作成効率10倍UP!明日から使えるプロンプト大公開
- 2024/04/23 2025年度奨学生 フルブライト語学アシスタント (FLTA) プログラム

Education News教育ニュース
英語教育に関するニュース・情報をピックアップして
お伝えしています。
英語教育に関するニュース・情報をピックアップして
お伝えしています。
- 2023/08/09 『変化のための英語教員研修のデザイン 明日からの授業が変わるための 16 の視点 』を発表
- 2023/08/05 令和5年度全国学力・学習状況調査の報告書・集計結果について
- 2023/06/23 長期研究プログラム「Future of English(英語の未来)」第一次報告書 (ブリティッシュ・カウンシル)
- 2023/05/19 令和4年度「英語教育実施状況調査」の結果について